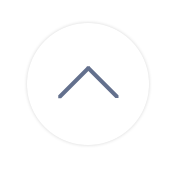日本は世界でも特に高齢化のスピードが速く、急速に「超高齢社会」へとなりつつあります。総務省が公開した資料「統計からみた我が国の高齢者」によると2024年9月15日現在、日本の65歳以上の人口は約3,625万人で、総人口に占める割合は29.3%、2040年にはこの割合が34.8%に上昇すると予測されています。
そんなシニア層を対象にマーケティングをおこなう際は、彼ら特有のニーズや行動特性を理解し、それに基づいた施策を展開することが不可欠です。
そこでこの記事では、シニア層向けマーケティングの基本知識やシニア市場の動向、そしてデジタル施策について解説していきます。
そもそも「シニア層」と「シニアマーケティング」とは?
マーケティングにおける「シニア層」には明確な定義があるわけではありません。ただ、日本や世界保健機関(WHO)を含む多くの公的機関では、65歳以上を「高齢者(シニア)」と定義しています。
現在、わが国では65歳以上を高齢者、そのうち65~74歳を前期高齢者、75歳以上は後期高齢者と定義している。他国を見ても60歳以上を高齢者としている国もあるが、多くの国は65歳以上のようである。
高齢者は何歳?|日医on-line
日本は世界でも類を見ない速さで高齢化が進展しており、2025年には団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者となります。高齢化率は30%を超えると予測され、それに伴いシニア層市場の規模も急速に拡大しています。

シニアマーケティングは、そんな65歳以上の高齢者層(シニア世代)を主な対象として、製品やサービスの開発、プロモーション活動などをおこなうマーケティング手法です。
シニアマーケティングが企業にとって重要な理由
現在では以下のような背景から、企業のマーケティング活動でも重要視されています。
- 日本経済において、シニア市場は数少ない成長市場となっている
- 年齢や健康状態など、さまざまな条件で市場が細分化されている
1. 日本経済において、シニア市場は数少ない成長市場となっているから
高齢化が進む日本経済において、シニア市場は成長市場として見られています。
以下は、みずほ銀行産業調査部がおこなったシニア層向け市場の調査の引用です。これによると、シニア市場は2025年に100兆円規模に拡大すると推計されています。
高齢者向け市場は高齢者人口の変化におい自他需要増加に伴い、2025年には101.3兆円規模(2007年対比161%)に成長し、国内需要を牽引する市場になると予測している。(中略)生活の質を向上する教養・娯楽等にも波及が及ぶうえ、卸・小売や運輸・広告等間接的に影響を受ける産業が多いことが特徴である。
高齢者向け市場 ~来るべき「2025年」に向けての取り組みが求められる~|みずほコーポレート銀行 産業調査部
他世代の市場が縮小傾向にある中、今後も拡大していくと見られているシニア層は、購買層として無視できない存在となっていくでしょう。仮に競合他社がシニア層に本格的なアプローチをしていない場合、早期にシニア市場を掴むことで、差別化を図れます。
2. 年齢や健康状態など、さまざまな条件で市場が細分化されているから
総務省が2013年に公開した「情報通信白書 変わる高齢者像 -アクティブシニアの出現-」にもある通り、現代のシニア層には旅行や趣味、自己投資に積極的な「アクティブシニア」が増えています。
この「情報通信白書」の調査自体は2013年のものですが、ここで取り上げられたシニア層の傾向については、現在でも顕著なものです。
-
 石川 優二
石川 優二
-
例えば、私の知人の中には80代前半でも外車でドライブを楽しんだり、娘さんや友だちと海外旅行へ行ったりする方がいます。
また、60代後半になる方にもアーティストの追っかけをしたり、流行りのスイーツを買うために行列に並んだり、テーマパークに朝一番で出かけて満喫したりしている方もおり、まさに言葉通り「アクティブ」なんです。
そのため、もしこのアクティブシニア層へのアプローチに成功すれば、新たな市場機会を得られる可能性があります。

一方で、高齢化の進行に伴い、身体的・精神的な機能低下による制約を抱える層も存在します。実際には、年齢や健康状態、ライフステージ、デジタルの活用度など、多様な条件でシニア市場は細分化されているのです。
こうした現状から、冒頭でも触れた通りシニア層の特性やニーズを細かく把握し、ターゲットに合わせた施策を検討するシニアマーケティングは、企業において重要度を増しているのです。
最大のポイントは「シニア層だから」と一括りにしないこと
シニアマーケティングをおこなう際のポイントは、シニア層を「シニア層」として一括りにしないことです。
シニア層は年齢や健康状態、生活環境、価値観、デジタルリテラシーなどによって多様化しており、前期高齢者(65歳から74歳)と後期高齢者(75歳以上)の間でもライフスタイルや身体状況が大きく異なる場合があります。
-
 石川 優二
石川 優二
-
現に私の周りにも、70代で毎週テニスやウォーキングに励んでいたり、フルマラソンに挑戦したりと若々しく活動する人がいる一方、同じ70代でも外出を最低限に抑えて家で過ごすことが多い人もいます。
どちらも「シニア」という括りには入りますが、行動特性やニーズが大きく異なるのが分かりますね。
また、同じシニア世代内でも、団塊世代とそれ以前の世代では育った時代背景やテクノロジーへの親和性が異なるため、広告やプロモーションにおける訴求内容をそれぞれ変える必要があります。
シニア層のインターネット利用率に見る、先入観で施策を考える危険性
シニアマーケティングに取り組む企業が陥りがちな誤解の一つに、「シニア層はデジタルに疎い」という固定観念があります。たとえば、「シニアには紙のチラシやカタログだけで十分」あるいは「アプリの利用は難しい」といった先入観から、オンライン施策を敬遠してしまう・・・といったケースです。
ただ、総務省の「令和5年通信利用動向調査」によると、60代のインターネット利用率は90.2%、70代でも67.0%と高く、実際には多くのシニア層がデジタルになじみがあることが明らかです。

LINE や YouTube といったデジタルサービスの普及も進んでおり、2022年7月に実施された調査では、65歳から69歳の男性の LINE 利用率が64.1%、女性だと70.9%となっています。

「紙だけでいい」や「アプリは無理だろう」と決めつけるのは、シニア層の実態を的確に捉えているとはいえないのです。
シニア層の多様性をふまえたアプローチに欠かせない市場分析
シニア層向けマーケティングではターゲットユーザーの特性やニーズを把握し、ターゲットに合わせた施策を検討することが欠かせません。
たとえば、旅行や趣味、自己投資に積極的なアクティブシニア層には余暇や学びの機会を訴求する施策が有効である一方、身体機能に不安を感じる層には、バリアフリー環境の整備や、医療・介護、日常生活支援といった具体的なサポート体制の充実が求められます。
こうしたシニア層の多様性をふまえたアプローチをおこなうために欠かせないのが、セグメンテーション(市場の細分化)やペルソナの設定(具体的なターゲット像の描写)です。
▼セグメンテーション(市場の細分化)を詳しく知りたい方はこちら
セグメンテーションとは?分類基準や活用時に意識すべき4Rも解説|キーマケのブログ|株式会社キーワードマーケティング
セグメンテーションとは、マーケティングや広告の戦略を構築する際に、不特定多数の人を「特定の基準」で分けることを指します。
たとえば、アクティブで健康的な60代には趣味や余暇の充実を訴求するオンライン広告が効果的な一方、デジタル操作に慣れていない70代後半以降の層には、地域のイベントや紙媒体を活用したオフライン施策を中心に据えるほうが適している場合もあります。
-
 石川 優二
石川 優二
-
たとえば、前者に向けた施策なら Instagram や YouTube といった SNS を活用、後者に向けた施策ならカルチャースクールや体験イベントの案内を新聞の折り込みチラシに入れ、電話や郵送で申し込みを受け付けるといった方法が考えられますね。
また、チラシに必要に応じて QR コードを添え、「会場周辺の地図をスマホで確認できます」などの案内を加えることで、どちらの層にも安心して利用しやすくなるでしょう。
つまり、「シニアだから」と一括りにして施策を考えるのではなく、統計情報や市場調査、顧客アンケートやヒアリングなどのデータに基づき細分化したうえで、各セグメントに最適化したマーケティング施策を考えることが、シニア層市場で成果を上げるための大切なポイントとなるのです。
シニア市場におけるデジタルマーケティング施策の7つのポイント
シニア層のデジタル活用が進んでおり、企業にとってはオンラインでの接点を確立することの重要性が一段と高まっています。
そこでここからは、シニア市場に特化したデジタルマーケティング施策のポイントとして、以下の7つを紹介します。
| シニア層向けデジタルマーケティングの7つのポイント |
|---|
| 1. 検索連動型広告のキーワードはシンプルに、分かりやすく 2. 広告画像はフォントを大きく、コントラストをしっかりと 3. 分かりやすく丁寧なコピーライティングを心がける 4. 入力フォームの項目は、必要最低限に絞るべし 5. シニア層向けサイトは、シンプルかつ直感的に設計する 6. 「シニアだから」と敬遠せず、SNS や YouTube も活用する 7. オフラインイベントとデジタル情報を連携させる |
1. 検索連動型広告のキーワードはシンプルに、分かりやすく
シニア層のデジタル利用は着実に拡大しているものの、特に高齢の方々はデジタル操作に不慣れな場合も多いのが実情です。そのため検索時に入力されるキーワードは、直感的で短く、シンプルな表現が好まれる傾向にあります。

たとえば、「初心者スマホ」や「スマホの料金」のように、関心のあることをシンプルなフレーズで表すケースが想定されます。こうした場合、具体的な商品やサービス名に「初心者」や「料金」といった言葉を組み合わせることで、シニア層が探している情報に合致しやすい検索連動型広告の設計が可能になるでしょう。
こうした背景を踏まえると、シニア層をターゲットとする検索連動型広告では、分かりやすいキーワードを中心に設定することが、効果的なアプローチにつながると考えられます。
2. 広告画像はフォントを大きく、コントラストをしっかりと
シニア層は加齢に伴い視力や情報処理速度が低下しやすいため、広告クリエイティブは視認性と理解しやすさを重視した設計が求められます。
たとえば、フォントサイズは16px 以上に設定し、ゴシック体などのシンプルで読みやすい書体を採用すると、視力低下への配慮になることが期待できます。

また、背景と文字のコントラストを十分に確保し、黒文字に白背景といった明快なデザインにすることで、誰にでも見やすいビジュアルを実現できます。
3. 分かりやすく丁寧なコピーライティングを心がける
シニア層が新しい専門用語や流行のカタカナ語に馴染みにくい傾向があるため、コピーライティングにおいては以下の「NG 例」のような難解な表現や過剰なカタカナ語を避け、「OK 例」のように平易かつ丁寧な日本語を使うのがおすすめです。
| OK 例 |
この時計はあなたの心拍数をやさしく見守り、日々の健康状態を簡単に チェックできます。 操作がわかりやすいので、初めての方でも安心してご利用いただけます。 |
| NG 例 |
このデバイスは、最新のセンサーテクノロジーとハイパフォーマンスな データアナリティクスを融合。 シニアライフにおけるインテリジェントなウェルネスソリューションを 提供いたします。 |
こうした配慮により、情報がスムーズに伝わり、シニア層の理解が促進されます。
4. 入力フォームの項目は、必要最低限に絞る
シニア層向けのページで入力フォームを設置する場合、できるだけフォームをシンプルに設計することがポイントです。
シニア層は、加齢に伴う視力の低下やデジタル操作への不慣れさなどから、複雑な入力フォームに対してストレスを感じ、途中で離脱するリスクが高い傾向があるためです。

たとえば、必要最低限の入力項目に絞り、郵便番号入力時に住所が自動で補完される機能や、名前入力時にフリガナが自動表示されるような仕組みを導入することで、入力ミスを防ぎながら操作負担を軽減できます。
大きめのフォントや入力ボックスなどで見やすく整えるのも効果的
また、視認性を高めるには、以下の有料老人ホーム「ベネッセスタイルケア」入力フォームのように、大きめのフォント、明瞭な入力ボックス、目立つ送信ボタンなどを採用することが効果的です。

また、エラーが発生した際に具体的な修正方法をわかりやすく示すといった工夫もできると、ユーザーに安心感を与えられます。
5. サイトはシンプルかつ直感的に設計する
高齢者は若年層に比べてデジタル操作に慣れるまでに時間がかかるため、サイト全体のナビゲーションはできるだけシンプルで直感的な設計が求められます。
たとえば、以下の通販サイト「ハルメク」のように「無料カタログ」や各商品カテゴリといった主要なセクションを大きく明確なボタンや固定のナビゲーションバーで表示し、利用者がどのページにいるのか一目で分かるよう工夫しましょう。

また、ページ内の情報は適切に整理し、段落や見出しを用いて必要な内容にスムーズにアクセスできるようにすることも大切です。
さらに、エラーが発生した際や操作に迷った場合には、問い合わせ窓口や電話番号を目立つ位置に配置し、ユーザーが安心して利用できるサポート体制を整えることで、サイト全体のユーザビリティの向上にもつながります。
6. SNS や YouTube も活用する
シニア市場におけるデジタルマーケティングでも、SNS の活用は検討できる施策です。
例えば、NTT ドコモ モバイル社会研究所の調査結果によれば、60歳から79歳のシニア層における LINE の利用率は76%であり、同調査でのメール利用率64%を初めて上回りました。
LINE は家族や友人とのコミュニケーションの主要手段として広く定着しています。こうした背景を踏まえると、企業が検討できる施策として挙げられるのは、公式アカウントを活用したクーポン配布やイベント案内、予約リマインド通知などです。
また、YouTube もシニア層の利用率が極めて高いというデータがあります。

シニア層は、趣味や健康、生活の知恵に関する情報を動画で収集する傾向もあるといわれています。さらに現在では「Earth おばあちゃんねる」のようにシニア層のユーチューバーも活躍しており、自身と同世代の方の活躍に勇気づけられている方も多いでしょう。
こうしたシニア層を対象に動画を作成する際は、情報がより分かりやすく伝わるよう、以下のようなポイントを押さえた動画を作成することが大切です。
- ゆったりとしたテンポの動画にする
- 見やすい字幕を付ける
- ナレーションの音声は聞き取りやすくはっきりとしたものを採用する
このように、LINE と YouTube を中心としたオンライン施策も取り入れることで、シニア層ユーザーのエンゲージメントの向上やコンバージョン率の改善が期待できます。
7. オフラインイベントとデジタル情報を連携させる
シニア市場では、デジタル化が進む中でも、新聞や折込チラシなどの紙媒体やリアル店舗が依然として主要な情報源となっています。

これらのオフラインチャネルは、シニア層にとって信頼性と安心感が強いといえます。そのため、企業が考えたいのは、オフラインとデジタル施策を連携させ、シームレスにオンラインへ誘導できる環境を整えることです。
たとえば、店舗のチラシやパンフレットに「スマホのカメラで簡単に詳細情報をご覧いただけます」などの文言とともに QR コードを掲載し、デジタル情報へのアクセスを容易にすることで、利用者が安心してサービスを利用できるようにする取り組みが考えられます。

ただ、QR コードの操作に不慣れな層もいるため、オフラインとデジタルを連携させる際にはサポートが欠かせません。
-
 石川 優二
石川 優二
-
こうした場合の効果的なサポートとして、「実店舗で店頭スタッフが操作をサポートする」ことが挙げられます。
実際に画面を見ながら操作について教え、困ったときにサポートできる環境を整えることで、QR コードの読み取りに戸惑う方でも安心して利用できるようになります。
このように、オフラインとデジタルの相乗効果を意識した施策をおこなうことで、シニア層にとっても自社の商品やサービスを知ってもらいやすくなります。
今後はどの企業もマーケティングでシニア層を無視できない時代に
シニア層向けマーケティングは、ターゲットとして「高齢者」を明確に設定していない企業であっても、将来的に無視できない存在になるでしょう。シニア層の消費行動は家族や知人にも波及する可能性がありますし、高齢者に関する社会課題に合わせて、新たなビジネス機会が生まれる可能性もあるからです。
さらに、少子高齢化によって従来の主要ターゲット層が縮小する中、企業はシニア層やその上位世代の層も取り込む必要性が高まります。こうした背景から、今後シニアマーケティングの重要性は一段と増していくと言えるでしょう。
今後、みなさんがシニア世代を対象とした取り組みを検討する際に、この記事がシニア層向けマーケティングへの理解を深め、実践に役立つヒントになれば幸いです。
運用型広告を中心としたマーケティングの基本から応用まで学べる無料メルマガを配信しています。詳しくはこちらをご覧ください。
最新&実用的な運用型広告のノウハウを学び、実践する研究会です。相談、コンサルティングも対応。広告の問題やマーケティングの悩みを電話やZoomで相談できます。
メールアドレスをご登録いただけますと、広告・マーケティングの役立つ情報をお届けします。

- 運用型広告で成果を出すノウハウから、ランディングページの改善、マーケティング全般の基本と応用まで学べるメルマガです。
自社やクライアントさんの広告、マーケティング施策に悩みのある方に役立つ情報を配信しています。
メールアドレスをご登録いただきますと、ブログの更新情報などをお届けいたします。
- 「わかりにくいこと」を「わかりやすく」をモットーに、すべての記事を実際に広告運用に関わるメンバー自身が執筆しています。ぜひ無料のメールマガジンに登録して更新情報を見逃さないようにしてください!
記事を書いた人

インハウス支援室長
全国400社以上の研究会員の運用型広告・マーケティングコンサルティングを担当。養成講座では500人以上を教育。コンサル・講師・執筆業から、広告運用代行、ホームページ制作、システム開発まで担当。自社ビジネス成長のための製品開発、販売をする実践家でもある。自他ともに認める変わり者。徳島県出身。
関連記事
広告アカウント診断(無料)も実施中
私たちの分析力・提案力をお試しいただけます
広告アカウント診断(無料)も実施中
私たちの分析力・提案力をお試しいただけます
-
あなたの広告アカウントを無料診断します
広告アカウント診断 -
詳細なお見積りをご希望の方はこちら
お問い合わせ -
支援事例などをまとめたサービス紹介資料はこちら
サービス資料のダウンロードはこちら