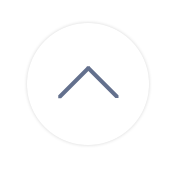企業間でおこなうマーケティング活動である「BtoB マーケティング」は、時代の流れとともに大きく変化しています。
これまではテレアポや訪問営業がメインだったのが、市場の競争激化やテクノロジーの進化、顧客ニーズの多様化などに伴い、今ではさまざまな手段が採用されるようになりました。
今回は BtoB マーケティングについてはじめて勉強する方向けに、BtoB マーケティングの全体像とプロセスを解説します。
BtoB マーケティングとは
BtoB(Business to Business)マーケティングとは、企業間で商品やサービスを販売するためにおこなうマーケティング活動のことです。一般消費者ではなく、企業がビジネスの顧客となります。
BtoB マーケティングでは、製品やサービスが企業の運営効率や生産性の向上、またはコストの削減に寄与することを重視し、企業のビジネスニーズに焦点を当てたアプローチが取られます。意思決定までに複数の部署や人が関与することもあるため、検討期間が長くなる傾向にあります。
BtoC マーケティングとの違い
BtoB マーケティングと比較対象となるのが、一般消費者を対象とした BtoC マーケティングです。
BtoB マーケティングと BtoC マーケティングにはビジネスのターゲットが異なることや、購入までの検討期間や検討プロセスなどに違いがあります。
以下は、BtoB マーケティングと BtoC マーケティングを「検討期間」と「検討に関わる人数」、「購入単価」、「購入の目的」の4つの観点で比較した表です。
| 項目 | BtoB マーケティング | BtoC マーケティング |
|---|---|---|
| 検討期間 | 長い | 短い |
| 検討に関わる人数 | 多い | 少ない |
| 購入単価 | 高い | 低い |
| 購入の目的 | 現状の課題解決 | さまざま |
まず、BtoB マーケティングは担当者一人の意思で製品を購入できません。購入に際して社内での確認を挟むケースが多いため、購入までの検討期間が BtoC と比較して長く、購入を検討する人数も増える傾向にあります。
企業対企業の取引になるため、BtoC と比較して購入単価も高くなりがちです。
また、BtoC マーケティングと BtoB マーケティングでは、製品購入の目的が大きく異なります。
BtoC マーケティングでは「自分の生活を豊かにしたい」や「今の生活をより便利にしたい」など多種多様な購入目的がある一方、BtoB マーケティングでは業務の負担軽減や効率化、ユーザーデータの整理など、基本的に企業が抱えている課題を解決することが購入の目的になります。
BtoB マーケティングのプロセス
BtoB マーケティングのプロセスは大きく以下の6つに分かれます。
- 戦略設計
- リードの獲得(リードジェネレーション)
- リードの育成(リードナーチャリング)
- リードの選別(リードクオリフィケーション)
- 商談
- 継続利用
ここからはそれぞれのプロセスについて説明していきます。
1. 戦略設計
まず、実際に施策の実行に移る前に、しっかりと戦略を立てておきましょう。BtoB マーケティングに限らず、マーケティング活動はむやみに施策を打っても成功する確率は低いです。
前述の通り、BtoB マーケティングは BtoC マーケティングと比較して検討期間が長く、検討に関わる人数も多く、購入単価も高い傾向にあります。そのためターゲットごとに異なる課題を理解し、課題を解決する方法を提案しなければ、受注に繋がりにくくなります。
戦略の立て方はさまざまですが、ここでは戦略設計の際によく使われるフレームワークの「3C 分析」について説明します。
3C 分析とは
3C 分析とは、市場/顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つを軸にして市場環境を分析するフレームワークを指します。
それぞれの軸で分析することと分析の目的については、以下の表の通りです。
| 3つの軸 | 分析すること | 目的 |
|---|---|---|
| 市場/顧客 | 市場のニーズ、顧客の行動、 購買動機、顧客のセグメント化 | 顧客のニーズを理解し、それにどのように応えるかを考える |
| 競合 | 市場における主要な競合他社とその戦略、強みと弱み、 市場での立ち位置など | 自社の競争上の優位性や差別化ポイントを見つけ出し、市場での自社のポジショニングを明確にする |
| 自社 | リソースや能力、強みと弱み、 価値提案など自社の内部状況 | 自社の現状を正確に理解することで、戦略的な方向性を定め、実行可能な計画を 立てる |
3C 分析についてはこちらの記事でも詳細に解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
ベテランが解説!広告運用開始後にこそ活用したい「3C分析」とは|キーマケのブログ|株式会社キーワードマーケティング
今回の記事では、広告運用時に用いる3C 分析を紹介します。具体的には、広告運用をする中で、「お客様の成果」に大きな変化が見られたときに、何が要因だったかを探るためのものです。
2. リードの創出(リードジェネレーション)
戦略設計が完了したら、いよいよ施策の実施に入ります。最初におこなうのは「リード」と呼ばれる見込み顧客の創出です。これを「リードジェネレーション」と呼びます。
リードジェネレーションの詳細については、こちらの記事を参考にしてみてください。
リードジェネレーションとは?Web 広告代理店が取り組んだリード獲得施策と成功事例|キーマケのブログ
リードジェネレーションにはさまざまな施策がありますが、はじめてリードジェネレーションに取り組まれる方はどれから手を付けてよいか分かりにくいと思います。 施策を選ぶときの参考になるよう、これまでキーワードマーケティングが実施してきた施策を解説します。
ここでは、BtoB マーケティングにおけるリードジェネレーションで有効な手法を2つ紹介します。
Web 広告
Web 広告は、インターネット上に掲載される広告のことです。代表的なものとして、Google や Yahoo! などの検索エンジンの検索結果に表示されるリスティング広告や、ブログやニュースサイトなどの広告枠に表示されるバナー広告が挙げられます。
Web 広告の配信を検討している場合は、リスティング広告から始めるのがおすすめです。リスティング広告は各検索エンジンの検索窓に入力された語句に対して広告を掲載できるため、欲しいものを能動的に探しているユーザーに広告を出せます。
ウェビナー
ウェビナーとは、オンラインでライブ配信されるプレゼンテーションや講義形式のイベントです。専門知識やノウハウを提供することで製品やサービスに興味を持つ可能性のある人々と接触し、リードを創出します。
ウェビナー開催には、参加したいと思ってもらえるテーマの選定が重要になります。リードジェネレーションにおけるウェビナーでは、初めて参加するユーザーへ向けて、業界の中で広く関心のあるトピックやホットな話題をもとにしたテーマを選びましょう。
3. リードの育成(リードナーチャリング)
リードを獲得した後は、見込み顧客の購買意欲を高めるためのリードの育成に入りましょう。このフローは「リードナーチャリング」と呼ばれます。
ここでは、リードナーチャリングの手法として有効なものを2つ紹介します。
メルマガ(メールマガジン)
見込み顧客に定期的に連絡を取ることで、自社サービスに対する関心を持続させます。
重要なことは見込み顧客に興味をもってもらえる内容を作成することと、顧客属性に合わせて配信タイミングや頻度を調整することです。
例えば、ビジネスマンを対象とした場合、朝の通勤時間や会社に着いてメールを確認するタイミングで配信することで開封してもらいやすくなります。
キーワードマーケティングでも、決まった曜日にブログ公開情報やセミナー開催情報を、希望したユーザーにメルマガ配信しています。特にセミナー開催情報は情報公開のタイミングだけではなく開催直前まで定期的に配信しています。

ウェビナー
リードジェネレーションでも紹介しましたが、リードナーチャリングにおいてもウェビナーは有効な手法です。自社サービスへのユーザーからの信頼を構築することができ、リードが顧客となる可能性を高めることができます。
リードジェネレーションでは、はじめて参加するユーザーに向けた比較的参加のハードルが低いテーマを選ぶのに対し、リードナーチャリングにおけるウェビナーでは、業界特有のテーマやニッチなテーマを選ぶことをおすすめします。
4. リードの選別(リードクオリフィケーション)
リードの育成をおこなっていくと、見込み顧客の中でも顧客となる可能性の高いリードと可能性の低いリードに分かれていきます。その中から顧客となる可能性の高いリード(ホットリード)を選別することが、リードクオリフィケーションです。
リードクオリフィケーションの方法として一般的なのが「スコアリング」と呼ばれるものです。これは、リードが起こした行動を点数化し、点数が高いリードをホットリードとする手法です。
例えば、ウェビナー参加で1点、資料ダウンロードで2点など、リードの行動それぞれに点数を設定し、一定基準の点数を超えたリードをホットリードとするというものが挙げられます。
5. 商談
リードの選別が完了したら商談のアポイントを獲得しましょう。日時が決まったらセールス部門に引き継ぎ、商談を実施します。
効果的な商談を実施するためには、商談までのリードの行動の振り返りや、あらかじめアポイント段階でリードが抱えている課題感などをヒアリングしておくことが重要です。
6. 継続利用
商談の結果受注に至ったとしても、まだ企業同士の付き合いが始まったに過ぎません。BtoB マーケティングは受注したら終わりではなく、継続してサービスを利用してもらうことが重要です。
サブスクリプション形態などの継続利用を前提としたサービスであれば、顧客との良好な関係を維持し、満足度を保つ必要があります。
また、顧客とコミュニケーションを取る中で新たなニーズが出てくれば、クロスセルやアップセルのチャンスも生まれます。受注して終わりではなく、中長期的なコミュニケーションが重要になることを意識しましょう。
プロセスに沿った BtoB マーケティングには、ツールの活用も一つの手
紹介した内容からもわかる通り、BtoB マーケティングは複数の部門にまたがって実施されるものです。戦略設計やリードジェネレーションはマーケティング部の領域ですが、商談は営業担当の領域であることを考えると分かりやすいでしょう。
部署や担当者をまたいだ活動をスムーズにおこないたい場合は、マーケティングツールとして CRM、SFA、MA といったものを利用するのも一つの方法です。
それぞれのツールについてまとめた記事もありますので、ぜひ参考にしてみてください。
CRMとSFA、MAの違いとは?できることや代表的なツールも紹介|キーマケのブログ|株式会社キーワードマーケティング
CRM と SFA、MA は活用フェーズや導入目的、利用するユーザー層においていくつか違いがあります。
BtoB マーケティングの成功事例
最後に、キーワードマーケティングがオウンドメディアの立ち上げにより売り上げを増加させた事例として、オウンドメディア「キーマケのブログ」を紹介します。
「キーマケのブログ」では、広告運用者自らが記事を執筆し、広告運用における知識や成果を出すノウハウを公開しています。質の高いコンテンツを年間100本(月8~9本)のペースで公開する体制を整えており、オウンドメディアを立ち上げたことでお問い合わせの半数以上がブログを初期接点としていることが分かっています。
BtoB マーケティングの基本を理解し、施策を実行しよう
ここまでBtoB マーケティングの全体像を解説しました。まだ学び始めたばかりの方も、BtoB マーケティングが企業の成長にとって欠かせない取り組みであることを理解できたかと思います。
BtoB マーケティングの基本を理解できたなら、あとは戦略を立て、具体的な施策を立案し、実行に向けて行動あるのみです。今回紹介した以外にも有効な施策はさまざまあるので、自社のサービスや目標とマッチする施策を選定して実行していきましょう。
お困りごとはまずはご相談ください。広告に限らず、認知やPRなど幅広い施策提案が可能です。
- コンバージョン数やCPAといった広告の目標達成はもちろんですが、中長期的な事業成長を目的としたマーケティング施策もご支援しています。年商数千万円規模から10億円規模へ、業績向上をご支援した事例もございます。まずはお気軽にご相談ください。
メールアドレスをご登録いただきますと、ブログの更新情報などをお届けいたします。
- 「わかりにくいこと」を「わかりやすく」をモットーに、すべての記事を実際に広告運用に関わるメンバー自身が執筆しています。ぜひ無料のメールマガジンに登録して更新情報を見逃さないようにしてください!
記事を書いた人

広告運用 コンサルタント
2021 年入社。大学では理工学部に所属し、制御工学を専攻。また、陸上競技部(短距離走)で活動。キーワードマーケティング入社後、広告事業部に配属される。趣味は海外ドラマ鑑賞と小説を読むこと。おしゃれなカフェや居酒屋に行くことが好き。
関連記事
広告アカウント診断(無料)も実施中
私たちの分析力・提案力をお試しいただけます
広告アカウント診断(無料)も実施中
私たちの分析力・提案力をお試しいただけます
-
あなたの広告アカウントを無料診断します
広告アカウント診断 -
詳細なお見積りをご希望の方はこちら
お問い合わせ -
支援事例などをまとめたサービス紹介資料はこちら
サービス資料のダウンロードはこちら